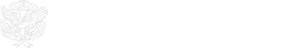剣
道剣道のお話
剣道のお話
小指の極意について
名誉師範 友川 紘一
「小指の極意」について説明します。
この言葉については、古来口伝が多く、こまかに書かれたものがみかけません。これは、「手の内の冴え」に関係してくる言葉と推察いたします。「手の内」「冴え」については、種々な教本にまた多くの先生方がお話をしているので、松原剣道の剣友の皆様にはすでに理解していることと思われます。
そこで、この機会を活用して、警視庁の先生方の教え、また多くの先生からの教えを基に考察いたしましたので、剣友の皆様の修行の糧にしていただければ幸甚に思います。剣道に「手の内」という言葉があります。これは、
1.竹刀の柄を持つ左右の手の持ち方
2.力の入れ方
3.打突の際の両手の緊張の状態と釣り合い
4.打突後の両手の解緊の状態
の四つのことを総合的に言ったものです。
次にこれらのことを具体的に説明したいと思います。
(1)竹刀の柄を持つ左右の手の持ち方
左手は柄頭から小指が出ないようにいっぱいに持ち、親指と人差し指との間の中央が竹刀の弦の線上にあるように持つ。
右手は鍔元を少し離して軽く握り、左手と同じに親指と人差し指との間の中央が、弦の線上にあるように持つ。それで自然に両手の手首は外側に折れて(右手首は「く」の字のように、左手首は「く」の字の反対のように、胸の前で合掌する状態)持つようにします。
両手の人差し指は軽く添える程度にし、親指は下方を向くように柔らかに握り、両腕の上筋をゆるくし、下筋をしめてふんわりと握り両肘は張らずしぼめず(紙一枚を挟む程度にする)自由自在に打突が打突ができるようにすること、左手と右手の握り間隔は約一握り半とすることが大事であります。
五輪の書「水の巻」太刀の持ちようの事の項の中に、
『太刀の持ち方は、親指と人差し指をやや浮かすような心持ちとし、中指はしめずゆるめず、薬指と小指をしめるようにして持つのである。手の内にゆるみがあるのは良くない。……能々心得べきものである。』
とあります。
高野佐三郎著書の「剣道」には、
『刀の持ち方は、右手は鍔より僅かに離し、左手は柄頭が半ば小指に掛るように握り、手の内は、鶏卵を握る心持ち極めて軽く握り、茶巾を絞る如くし、両腕に力を入れるべからず……』
とあるのを見ても、古来から剣道における竹刀の持ち方が重要であることがわかる。
(2)力の入れ方
両手の小指は普通に握りしめて、薬指、中指の方に行くにつれて力をゆるめて握り、人差し指は添え指とする。左拳の位置は、臍前より約ひと握りからひと握り半前にして、左手親指の付け根の関節を臍の高さにする。剣先の高さは相手の喉とし、延長は、顔の中心または左目とする。
手の内の力の入れ具合は、丁度鶏卵を握った気持ちで持つことが大切です。あまり力を入れ過ぎるとこわれるし、あまりゆるめて握ると落ちるから、その中間で握ります。肩や腕にはほとんど力を入れないようにします。
古歌に、「執る太刀の握り調子はやわらかに、しめずゆるめず小指離さず」とあるように、小指は適度な力の入れ具合を保っておきながらも柄からは離さないことが大事です。
力の入れ方に関する先人の教えをもう二つほど紹介させていただきます。
◎ 右をさき左をあとにやんわりと、手拭しぼるこころにて持て
◎ 太刀先の上れる人の手の内は、右よりかたき握りなるらむ
(3)打突の際の両手の緊張の状態と釣り合い
(4)打突後の両手の解緊の状態
(3)(4)は、運動の原則としての筋肉の緊張と解緊のことです。しかも、打突した際は、両手の手の内に均等に力を入れて、左右いずれにも偏らないようにすれば、釣り合いがとれて正しい方向で打突ができます。
すなわち、打突のときは、両手の手首を中心に動かして、内側に茶巾絞りの要領で絞り、充分に伸筋を働かす。また、打った瞬間は左右の親指を相手に向けて押し出すように締めることが大切です。(右手と左手が丁度良く、右足と左足が仲良く、手と足が仲良く調和させる)。
高野佐三郎著「剣道」では、『打つときには親指と小指とに力を入れて左右の手にて物を絞る気味に打つものとする。両腕に力を入れるべからず』と教えております。
打突後は元に復し、次の打突が容易にできるようにすることが大切です。
(古 歌)
◎ 撃つときは両の親指、薬指、小指の三つでしぼる心ぞ
◎ うつ太刀は一技二腕三気合四腹五心の法とこそ知れ
以上の手の内の作用の条件を満たし、瞬間的に手の内が充分に締まった打突に現れてくる力を冴えというのです。いくら竹刀が重くても、また力を強く加えても打突する瞬間が時間的に長ければ、決して冴えは現れてきません。
この手の内の冴えは、修錬の度合いによって大いに異なってくるものです。冴えは、手の内の締まりの現れであることはいうまでもなく、心気力の一致した打突によって生ずるものです。
(古 歌)
◎ 手の内の出来たる人の執る太刀は、心にかなうはたらきをなす
◎ それ剣は瞬息なり、心気力一致なり
このように小指の働きが、手の内の冴えた打突に結びつくことが理解していただけたのではないかと思います。持田盛二先生は、剣道の基礎を体で覚えるのに50年かかった遺訓に残されております。
手の内の冴えた打突は、朝に求めて夕べに得られるものではありません。良き師について素直に教わり、経験して会得し、体験して体得し、会得と体験をくり返して自得して頂きたいのであります。
宮本武蔵先生は、次のように教えています。
『今日は昨日の我に勝り、明日は下手に勝ち、後は上手に勝つと思って努力せよ』
と。
「立ち止まり、振り返り、またも行く一筋の道」。
松原剣道の剣友の皆さん「生涯剣道」といわれる我が国の伝統文化である剣の道を一歩一歩進もうではありませんか。
筆者も、手の内の冴えた打突を自得すべき、軽い木刀を使用し素振りで工夫しているところです。
稽古では、「気で攻め勝ち、理で打つ」ことを心がけ、三つの先の教えのうちの先の技を初太刀一本と課題にし、日々精進しているところであります。
参考文献
宮本武蔵 「五輪の書」
高野佐三郎 「剣 道」
堀籠敬蔵 「剣の道」「警視庁剣道教本」